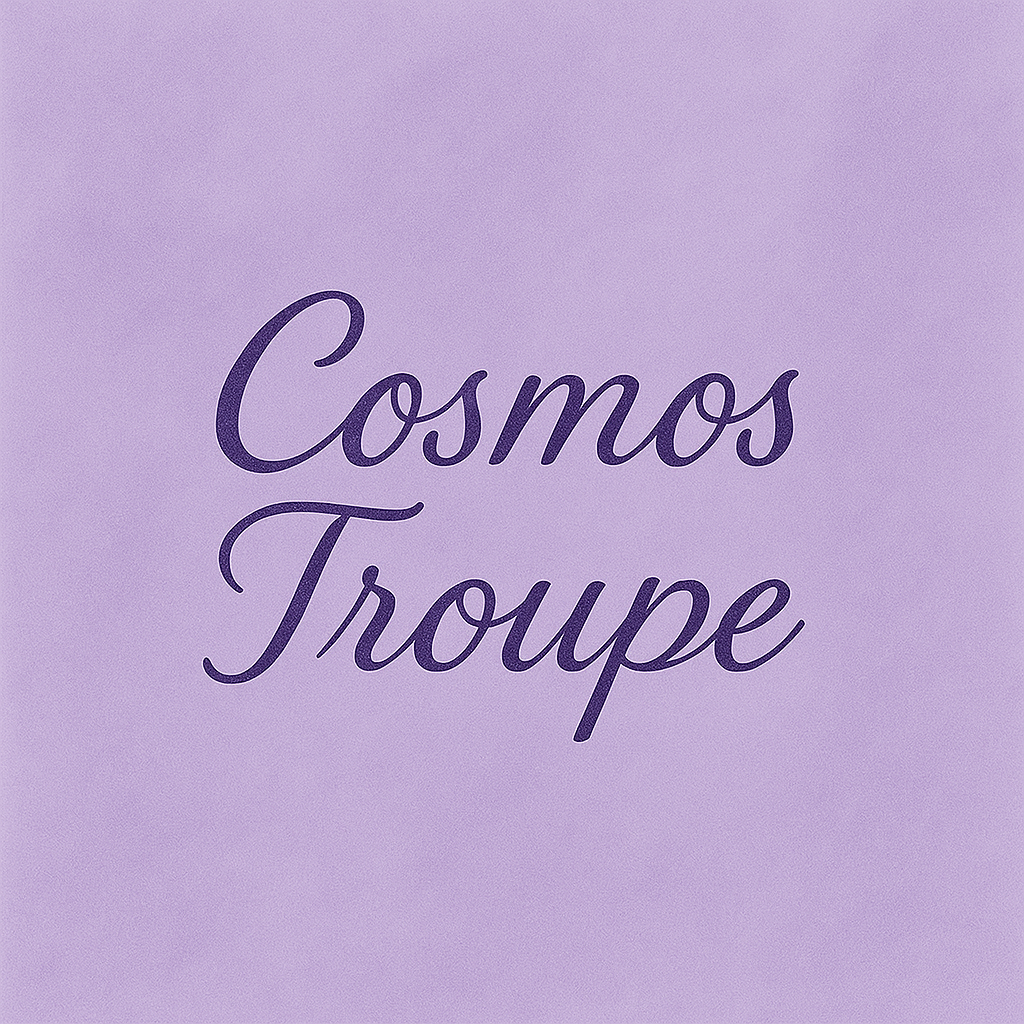
”海ゆかば”歌唱の中止
2025/9/24 宝塚歌劇にて上演中の
『BAYSIDE STAR』にて、
ずんちゃん(桜木みなと)
が歌唱している
「海ゆかば」という歌の
歌唱中止ニュースが流れてきました。
 |
宝塚歌劇団、宙組公演で使用の楽曲『海ゆかば』歌唱中止と差し替え発表 「様々なご意見を頂戴している」 …宝塚歌劇団は24日、現在公演中の宙組公演『BAYSIDE STAR』で使用している楽曲について、様々な意見を考慮し、歌唱の中止と楽曲の差し替えを行う… (出典:日テレNEWS NNN) |
宝塚大劇場では9/24の公演から歌唱中止。
東京宝塚劇場では楽曲そのものの差替えが決定しました。
この「海ゆかば」を巡っては、
公演初日から
”ずんちゃんに軍歌を歌わせるなんて…”
という意見も少なからずありましたが、
その声が大きくなってこのような事態になったと思われます。
対立する意見
「海ゆかば」に対する意見は、大きく二つ。
歌唱中止に否定的な意見
歌唱中止に否定的な意見の方は、
この曲の持つ本来の意味に焦点を当てています。
「海ゆかば」は単なる軍歌ではなく、
万葉集の大伴家持の和歌を元にした
鎮魂歌、
あるいは国家に殉じた人々への
哀悼の意を込めた歌
であるというものです。
このような視点を持つ方は、
宝塚歌劇団が批判に屈したことに対し、
「表現の自由の侵害だ」と強く非難していました。
また、一部の左派による圧力に屈した結果、
文化や伝統が失われていくことに危機感を抱いてる印象です。
さらに、「反戦」を掲げる人々が、
自らの価値観に合わない表現を排除しよう
とすることで、
皮肉にも全体主義的な流れを生み出しているのではないか
と指摘する声もあります。
海外の例を挙げる意見もありました。
例えば、宝塚の舞台では頻繁に利用される
フランスの国歌「ラ・マルセイエーズ」や、
アメリカの国歌「星条旗」も、
元をたどれば激しい戦闘や戦争を背景に作られた「軍歌」だということ。
しかし、これらの楽曲が使用されても批判の声はあがりません。
なぜか。
つまり、今回の「海ゆかば」への批判は、
特定の文化や歴史に対する偏見
に基づいているのではないか?
という意見でした。
うん、フランスの国歌「ラ・マルセイエーズ」の歌詞はすごいですよね…
行こう 祖国の子らよ
栄光の日が来た!
我らに向かって 暴君の
血まみれの旗が 掲げられた
血まみれの旗が 掲げられた
聞こえるか 戦場の
残忍な敵兵の咆哮を?
奴らは汝らの元に来て
汝らの子と妻の 喉を掻き切る!
これはまぎれもない軍歌だね( ゚Д゚)
あ、国歌でした。
歌唱中止に肯定的な意見
一方で、歌唱中止を肯定する人々の意見も。
たとえ鎮魂歌としての意味合いがあったとしても、
戦時中の「軍歌」として広く認識されているこの曲を、
華やかで多様な客層を抱える宝塚の舞台で使用すること自体が不適切だったと見ています。
こちら側の方は、
演出家や劇団のチェック体制の甘さ
を指摘していました。
作品制作の過程で、
なぜ誰もこの楽曲の起用が
物議を醸す可能性があると
気づかなかったのか、
という疑問です。
特に、ファンからは
「新生宙組の門出を祝う公演に、わざわざ論争の種を持ち込む必要があったのか」
という声も上がり、
中止によって安心して公演を楽しめるようになった
という安堵の声も聞かれました。
今回の「海ゆかば」歌唱中止は、
単なる舞台演出の変更という枠を超え、
表現の自由のあり方、
歴史認識の多様性といった、
現代社会が抱える根深い問題を
浮き彫りにしたように思います。
海ゆかばの歌詞と意味・背景
ここで、楽曲「海ゆかば」の歌詞と解釈をば…
「海ゆかば」は、日本の楽曲であり、
その歌詞と解釈については歴史的、
文化的な背景から様々な議論があります。
歌詞
海行かば 水漬く屍
山行かば 草生す屍
大君の 辺にこそ死なめ
かえりみはせじ
歌詞の解釈
この歌詞は、
万葉集に収められた大伴家持の歌
から取られています。
元々の歌は、
天皇への忠誠心と、
国のために命を捧げる覚悟
を表現したものです。
「海行かば 水漬く屍(かばね) / 山行かば 草生す屍(かばね)」:
この部分は、「海で死ねば水に浮かぶ屍となり、山で死ねば草むらに埋もれる屍となるだろう」という意味です。
これは、どこで死のうとも、天皇のため、国のために命を捧げる覚悟を象徴しています。
「大君(おおきみ)の 辺(へ)にこそ死なめ」:
「大君」は天皇を指します。「辺にこそ死なめ」は、「天皇のそばでこそ死にたい」という強い決意を表しています。
これは、死ぬ場所さえも天皇への忠誠心に捧げるという、極めて強い帰属意識と献身の精神を示しています。
「かえりみは せじ」:
「かえりみ」は、「振り返ること」や「後悔すること」を意味します。
「せじ」は否定を意味するため、「振り返ることはしない」「後悔はしない」という決意を表しています。
楽曲の歴史的背景と解釈の変遷
「海ゆかば」は、特に第二次世界大戦中、軍歌として広く知られるようになりました。
戦時下では、この歌が兵士の士気を高めるためのものとして積極的に利用されました。
その結果、多くの人々にとって「海ゆかば」は、戦争と結びつく象徴的な存在となりました。
戦後、この歌は、戦争を美化するものとして批判される一方で、戦争で命を落とした人々を鎮魂するための歌として解釈されることもあります。
今回の宝塚での一件でも、この二つの異なる解釈が対立しました。
鎮魂歌としての解釈:
戦争で命を捧げた兵士たちへの鎮魂や、彼らの犠牲を悼む歌として捉える見方です。
この解釈では、歌の持つ「天皇への忠誠」という側面よりも、「国のために命を捧げた人々の死」に焦点を当てています。
軍歌としての解釈:
この歌が戦意高揚に利用された歴史的な事実を重視する見方です。
この解釈では、歌そのものが持つ意味合いが、戦争を肯定し、美化するものとして受け止められる可能性があると警鐘を鳴らします。
このように、「海ゆかば」は、その歌詞が持つ普遍的な忠誠心や献身の精神と、戦時中に果たした特定の役割によって、多様な解釈と議論の対象となっています。
大きな声では言えないけど…
今回、こんなにも激化した理由の一つとしては最近の「日本人」の「日本」に対する「認識の変容」が挙げられるのかなぁなんて思ったり。
今までも「日本」や「日本を守る人」を敬ったりすると左派の方たちが怒ってイベントが中止に追い込まれたり…なんてことがよくありました。
「日本」=「軍国主義」みたいな変な思想がある人は少なからずいて、まぁ戦後はそういう教育も強かったような気がするんです。
私も君が代斉唱の時に起立しない先生から社会教わってましたwww
今思えば終わってるw
で、特に右派ではない人からすると「またやってんな~」くらいの感じでした。
でも最近、「国」を脅かす存在への畏怖が急激に高まる事案が欧州で多く起こり、その余波が日本にも及びそうになってますよね。
今まで対岸の火事だったことがいきなり自分の家の火事になろうとしている今、特に右派でない人たちは「日本の文化」を壊そうとする人たちへの嫌悪感が露わになっているような気がします。
だからこそ、今まで左派の大きい声に対してスルーしてた人たちの意見もガンガン出てきて、ぶつかり合った気もします。
今回、「海ゆかば」は軍歌に値し、不適切だということで批判が相次ぎ楽曲の使用が中止になりました。
でもマジのマジで使ったらだめな楽曲だったら最初から使われないと思うんですよね~
ショーを作った先生の意図もあるし、戦後80年という大きな節目に鎮魂の意味を込めていたのかもしれない。
海がテーマのショーで、海で散った命も多くあるだろうしね。
まぁその辺はわからないのですが、
個人的には将来、日本の文化の一つでもある宝塚歌劇が
あらゆる方向に配慮するのが当たり前
みたいなことになって欲しくないなぁと思います。
究極の話ですが、
昨今にぎやかになっている「豚肉」「土葬」と同じように、
「偶像」を禁止している方々に配慮したら宝塚歌劇は上演できなくなります。
まぁなんというか…
私は正直、日本の万葉集から取った歌を歌うずんちゃんも見たかった( 一一)
<PR>
<PR>魔除け
































